先日観た、100分de名著。
ハンセン病を患い、社会から隔離された施設で執筆された北條民雄のエピソードがぺったりと脳裏から離れず、ふと思い出しながら、妙な余韻を感じています。
作者の北條民雄(1914-1937)がハンセン病に罹患したのは十八歳のとき。東京東村山のハンセン病療養所「全生病院」への入所を余儀なくされます。現在では極めて伝染性の低い病であることがわかり治療法が確立しているハンセン病ですが、当時の患者たちは、圧倒的な差別と偏見に晒されていました。一度感染すると社会から完全に隔離され、後は死を待つしかない病とみなされる中、作者の北條は、作品を通して自らの絶望的な状況を見つめぬきました。その果てに北條が見出したのは「苦しみや絶望の底にあってなお朽ちない、いのちの力」。それでも絶望を拭い去ることはできませんでしたが、北條は、最期の最期まで生き抜こうという意志を、執筆を通してつかみとっていきました。
引用元:名著127「いのちの初夜」北條民雄 – 100分de名著 – NHK
戦時中、国家的な強制隔離政策も実施され、北條民雄自身も当然家族からも絶縁。北條民雄は発症前年に結婚するも破婚。
絶命を意識するほどに「生きよう」としてしまう自らの性と向き合い筆をとり続け、川端康成に見出され文壇に入るのですが、入所4年後の23歳の若さで亡くなります。
作品が発表されてもなお、親族からは本名は公にされていなかったらしく、当時のハンセン病患者が社会から断絶され、存在そのものがなかったものとされていた社会背景には異常さを感じる反面、無知故、そうせざるえなかった社会の同調圧力も相当だったのだと思います。
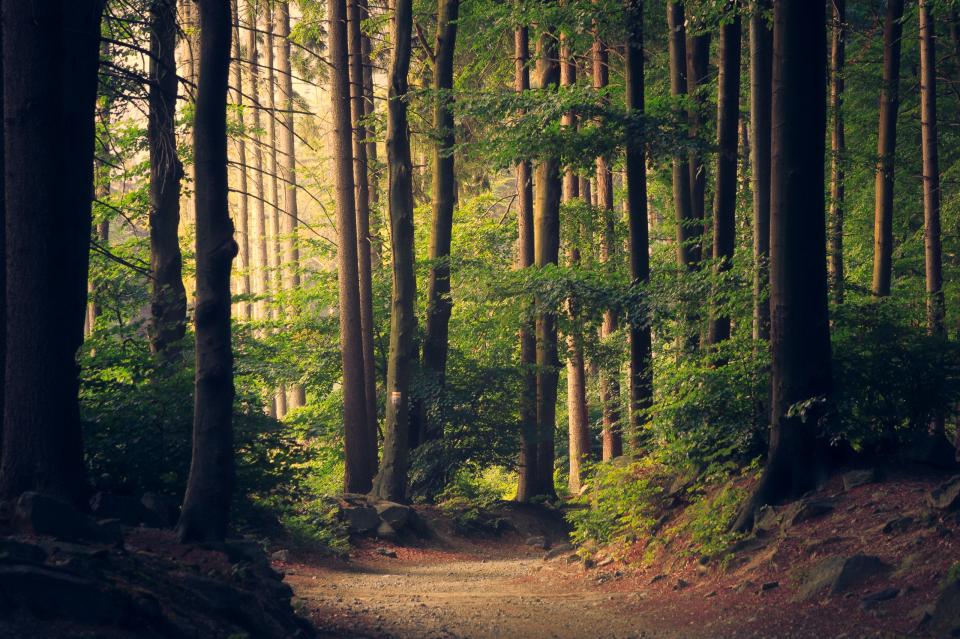
しばらく絶版していた作品が半世紀ぶりにコロナ禍で復刊したというのも、この作品が現代に通じるからなんでしょうね。
文壇に評価され、北條民雄が一度だけ施設を出て、鎌倉にいる川端の元を訪ねるのですが、感染力が低いことを知る川端は、北條と駅前の蕎麦屋で会食をした。というエピソードがとても印象的でした。
コロナ禍にも通じる部分ですが、つい罹患した人を人としてではなく病気そのものとして禁忌してしまうのですが、知性の高さというのは、こうした振る舞いにでも現れるものだなあと感心しました。
戦時中ということを勘案しても、隔離政策の背景にある優性学的偏見からうまれた優性保護政策が、法律として1996年まで続いていたというのも、まだまだ、この話が遠い過去の話になりきれていないことを暗喩している気もします。
隔離され生き場はあっても行き場のない終着点。
悲劇だけなく、希望や生きることの意味も含めて、心を揺さぶる話でした。